2023年12月9日。
この日は塩尻ワインサークル コミュニティヴィンヤードの年内最後の活動でした!
塩尻の最高気温は17度と予想され、季節外れな暖かさです。
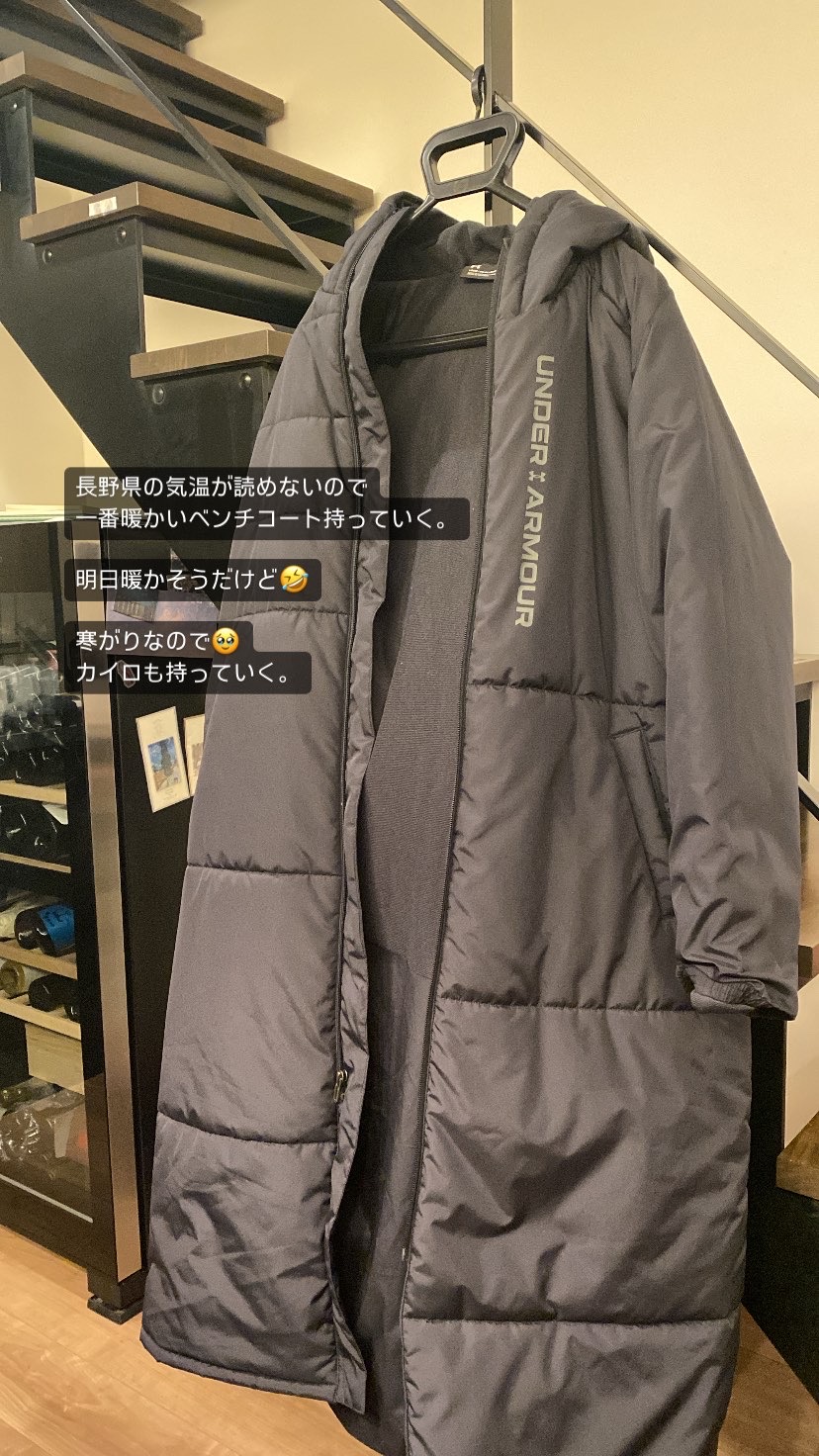
とはいえ朝・夕方の冷え込みや風による急激な気温の変化が怖かったので、ベンチコートとカイロを持って行きました。
結論、暑すぎました。笑
暑がりの方はもはや半袖で作業する始末でしたよ。
さて、それはさておき。今回は予め余裕を持ってあずさの座席を予約したので、1列のみの席を取ってみました。

こんな感じで、ベビーカーを横付けできてかなり楽チン!
帰りのチケットは直前に取ったため、通常の2列席に。
長女がベビーカーで寝てしまったので車両の連結部分で何十分も立っていたのですが、車内販売の方が「空いていれば1席のところに変更しましょうか」と声をかけてくださいました。この席があるのが塩尻方面からだと10号車で(行きは2号車でした)、帰りのチケットの座席が2号車あたりだったので移動が大変に感じてお断りしましたが、この対応から見るにベビーカー横付けも全然OKみたいです。(行きも特に何も言われませんでした)
コンセントが見つからなくて一瞬焦ったのですが、座席横についているタイプでした。

作業前にはいつも通り、111vineyard 川島さんから作業のレクチャーを受けます。
藁巻きの一番の目的はブドウの樹や芽を護ること。
特にまだ細い若樹は寒さに弱く凍害を被りやすいので、定植から4〜5年程度はこのようにしっかり藁巻きをして冬を越すのだそうです。
地際がもっとも冷えるため、根本近くをしっかり覆うのがコツ。
こちらはNG例です。単に藁を樹に沿わすだけでは、地際の保温はできません。



上手な巻き方はこちら。
藁の根本を折ってL字型にし、地面から樹の根本をしっかりと覆います。
折り曲げて寄せることで、地際を温めることができます。



また、風が吹くと藁がバラバラになるので、少しキツめに縛ることも重要だそうです。
ちなみにこの藁は、川島さんの奥様のご実家からいただいた「はぜかけ米」だそうです。


実は今、藁を手に入れるのも大変なんだとか。その理由は、単に米農家が減っているというだけではなく、米づくりが機械化したことにも起因しており、藁が少ないんだそうです。
昔ながらの手作業では、収穫した稲は田んぼに組んだ枠に束ねた稲をかけて天日干しで乾燥(はぜかけ)させてきたそうです。今回使わせていただいた藁は、この乾燥した稲なんですね。
ところが、近年は収穫した稲を機械乾燥させることが多くなりました。機械乾燥の前に脱穀(稲を米と藁に分ける)してしまうため、乾燥した藁ができないということになります。
特に山梨など、米の生産量がそもそも少ない産地ではさらに藁の調達は難しくなり、藁をわざわざ購入する生産者も多いそうです。(令和4年の米の都道府県別生産量ランキングでは、長野県は第13位の187,300t、山梨県は第43位の25,500t)
塩尻でも最近新規に設立された、とあるワイナリーでは藁を購入したそうです。その総額は15万円にも及んだとのことです。だいたいひと束50円程度で、一つの樹に大してふた束必要なので、ブドウ樹一本あたり100円がかかる計算になります。
保温して冬を越す目的であれば、断熱材を用いることも選択肢として挙げられます。
ただし、藁と断熱材には決定的な違いがあります。
それは、保湿力。
藁には保湿効果があるので、芽の乾燥も防ぐことができるそうです。
というわけで、せっせと作業し、2時間程度で作業は終了しました。


来年(3年目)からは2房ずつくらい、収穫できるかなーなんてお話もありました。
今からとっても楽しみです!

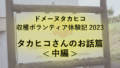

コメント